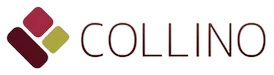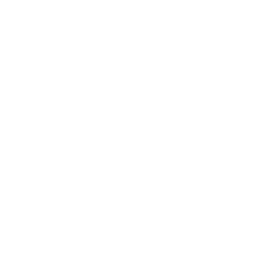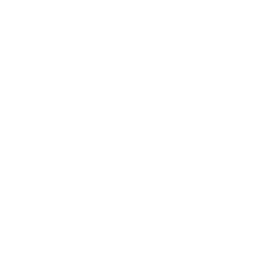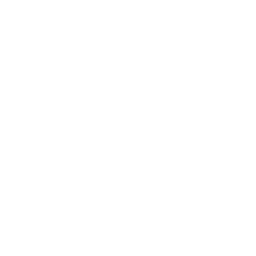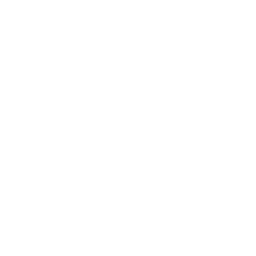「子ども部屋おじさん・おばさん」一級建築士が提案する、子どもを自立へ導く“子ども部屋”のつくり方

就職しても結婚しても実家を出ず、子ども部屋で暮らすまま中年になってしまう――いわゆる「子ども部屋おじさん」「子ども部屋おばさん」の存在が、SNSやメディアで話題を集めています。
実家暮らし自体は社会に悪影響を及ぼすものではありませんが、親の立場からすると、子どもには自立して家庭を築いてほしいという思いもあるでしょう。
では、どうして「子ども部屋おじさん・おばさん」は増えているのでしょうか。そして、これを避けたい場合、子ども部屋をどのように設計すればよいのでしょうか。
この記事では、一級建築士として数多くの住まいづくりをサポートしてきた住まいコンサルティングのプロが、子ども部屋づくりのポイントを提案します。
なぜ「子ども部屋おじさん・おばさん」が増えるのか?
● 実家が“快適すぎる”環境
子ども部屋で育った人が実家に居続ける理由の一つに、「居心地の良さ」が挙げられます。家事や生活費を親がカバーしてくれるうえ、部屋自体が広く快適であれば、わざわざ一人暮らしに踏み切る必要性を感じにくいのです。
とくに一昔前よりも、“子どもが育ちやすいように”広めの個室を与えられた世代が大人になることで、実家=最高の住環境というイメージが根付いているケースも多いと考えられます。
● 経済面の負担が重い
現代は、賃貸や住宅ローンの負担が重い社会状況でもあり、若い世代が一人暮らしや結婚を選ばず、実家で経済的に安定した生活を続けようとする傾向があります。もちろん経済的な合理性は否定できませんが、「快適な子ども部屋」「安定した親のサポート」が揃えば、余計に離れにくくなるのは自然な結果かもしれません。
● 親側の“手元にいてほしい”心理
実は、子ども部屋おじさん・おばさんが増える背景には、親自身が子どもを手放したくないという心理も隠れています。子どもが巣立つと孤立感を覚える親も多く、子どもの部屋を快適なまま残すことで、「いつまでも一緒にいたい」という無意識の願望を満たしているケースもあるのです。
親としては自立・結婚してほしい…どうすれば「子ども部屋おじさん・おばさん」を回避できるのか?
「子ども部屋おじさん・おばさん」が社会的に悪いというわけではありませんが、親からすると「子どもには自立してほしい」「結婚して家庭を築いてほしい」と願うことが多いでしょう。そのためにはいくつかの“子ども部屋づくり”のポイントがあります。
●一級建築士が提案する“自立を促す子ども部屋”のポイント
(1) 「快適すぎる部屋」をあえて作らない
- 部屋の広さを適度に抑える
子どもが成長期を過ごすうえで必要なスペースは確保しつつも、“必要以上の広さ”や“TVやインターネットなどの贅沢な設備”を与えすぎないこと。あまりに快適な個室だと、独立へのモチベーションが下がってしまう。 - 日常の家事を共有できるレイアウト
たとえば洗面所やリビングを通らないと子ども部屋に行けない間取りにするなど、自然に家族が顔を合わせ、家の用事を手伝う動線に配置するのも手。行き来自体が負担など住まいに不満があれば「早く自分の家を持ちたい」という気持ちを持つ子も。
(2) “自分のテリトリー”と“家族の共有スペース”を意識させる
- 部屋に生活機能を詰め込みすぎない
冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機など、生活設備のすべてを子ども部屋に置くと“半独立状態”になり、家族とほとんど接しないまま快適に暮らせてしまう。そこまでは与えずに、食事は家族共用のキッチンやダイニングで行うなど、“家族の共有スペース”をしっかり使うよう誘導する。 - 収納スペースは“最低限+成長対応”
服や趣味の道具が増えすぎると、部屋で完結できてしまい外部との接点が減る。成長とともに変化する持ち物にも対応しやすい可変式収納を導入しつつ、際限なく物をためこまない環境づくりを。
(3) “巣立ち”を見据えた家具選びやレイアウト
- 高価な家具で部屋を豪華にしすぎない
「一度整えたからずっとこのままでいい」という状況は、子ども自身も「この部屋が自分のゴール」と感じてしまう。逆に、必要最低限の家具にとどめ、「独立したら自分の好きな家具を揃えられる」という未来設計に期待を持たせるほうが効果的。 - 引っ越しやすい家具・インテリアを選ぶ
いずれ巣立つ時に“最低限の荷物で部屋を出やすい”状態だと、独立のハードルが下がる。ベッドやデスクは比較的移動しやすいものにし、カーテンや照明などもシンプルな仕様が望ましい。
親が気をつけたい“言葉かけ”と“距離感”
部屋づくりだけでなく、親の言動やメンタル面のサポートも「子ども部屋おじさん・おばさん」を防ぐうえで重要です。
● 「ここは今はあなたの部屋だけど、いつまでもここで暮らすわけじゃないよね」というスタンス
- 甘やかすだけでなく、“独立”への期待を伝える
子ども部屋の快適性を確保しつつ、「いずれは自立するのが当たり前」という価値観を折に触れて会話で共有する。 - 社会的な経験を積む機会をサポート
アルバイトや留学、インターンなど、外の社会で経験を積む機会を尊重する姿勢を示すこと。子どもが家の外に目を向けるほど、自然に“外で暮らしたい”という思いが強まる。
● 親自身が“子離れ”の意識を持つ
- 過保護・過干渉は避ける
子どもが家にいるうちは「何でもやってあげる」「経済的にすべてをカバーする」という態度は、結果的に自立心を削ぐ要因になる。 - 夫婦で“子どもが巣立った後の暮らし”を楽しむ計画を
子どもが独立したあと、自分たちがどう暮らすかにワクワクできる親ほど、子どもの巣立ちを素直に応援できる。
まとめ:親子がともに納得する“子ども部屋”が未来を変える
- 子ども部屋おじさん・おばさんは悪い存在ではない
実家暮らしを選ぶかどうかは個人の自由です。しかし、親としては自立してもらいたい気持ちがあるなら、部屋の作り方や家庭の仕組みを見直す価値がある。 - 部屋を快適にしすぎず、家族共用スペースを上手に活用
個室を与えても、生活のベースを“家族で共有する場”に残しておくことで、過度に居心地が良くなりすぎない工夫を。 - 子どもの成長と将来像を親子で語り合い、“いつか巣立つ”意識づくりを
インテリアや家具配置だけでなく、親の言葉かけや距離感が、自立に大きく影響する。
「子ども部屋おじさん・おばさん」が増えている背景には、社会の変化や経済的事情、そして親の価値観も密接に関わっています。しかし、子ども部屋の設計やレイアウト、家庭のルールを少し変えるだけでも、子どもの自立を促すことは可能です。
親も子も、お互いが納得しながら成長していけるような住まいづくりこそ、これからの時代に求められる「子ども部屋」の在り方ではないでしょうか。
いつか子どもが堂々と自分の人生を切り拓き、「あの家で育って本当によかった」と振り返る日を目指して、いま一度、住まいの見直しを検討してみてはいかがでしょうか。