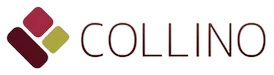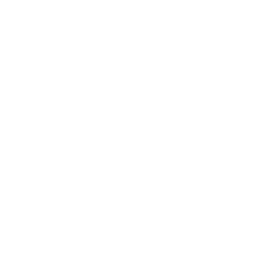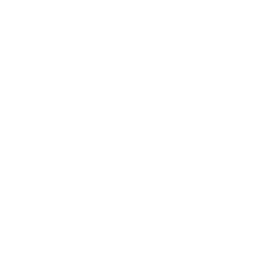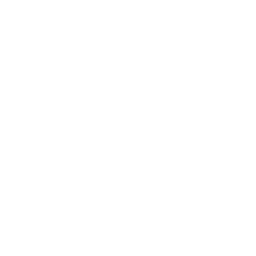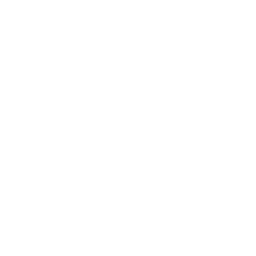散らかすことは、学びの第一歩― 子どもの発達過程から考える「子どもが片づけやすい家」
#インテリアコーディネート #ポジティブチェンジ #リノベーション #リビング学習 #一級建築士 #住まいの工夫 #子どもが片づけやすい家 #子どもの自立 #整理収納の仕組み #模様替え 東京 #発達心理学

「うちの子は、いつも部屋を散らかしてばかり…」
そう悩むお母さん、お父さんは少なくありません。
けれど実は、子どもが小さいうちに“散らかす”ことには、きちんと意味があります。
発達過程の観点から見れば、それは心と知能の発達に欠かせない行動なのです。
散らかすことは「世界を理解する練習」
子どもがモノを触ったり、動かしたり、並べたりするのは、
世界の仕組みを自分の手で確かめているからです。
「積み木を崩したらどうなる?」「入れ物に入れるとどんな音がする?」
こうした体験を通して、子どもは“因果関係”や“秩序”を学んでいるのです。
つまり、散らかすことは“混乱”ではなく、秩序を理解するためのプロセス。
この時期に十分に試行錯誤することで、「整理整頓」への理解が育っていきます。
発達段階に合わせて“片づけやすい仕組み”を
子どもの年齢や発達段階によって、「片づけの方法」は変わります。
親がやり方を教えるよりも、子どもが自分で片づけやすい環境を整えることが大切です。
🍼 幼児期(2~4歳):「出す」ことが楽しい時期
この時期の子どもは、まだ「元に戻す」という概念が育っていません。
ですから、片づけの第一歩は“簡単に戻せる仕組み”を作ることです。
- 「箱にポン」でOK。分類は1種類で十分。
- 箱やカゴに写真やマークなどのラベルを貼る(文字よりイメージが理解しやすい)
- 手の届く高さに収納を置く(親の助けが不要な位置)
例えば、「ブロック」「ままごと」「絵本」の3つの箱を用意し、
遊んだあとは1箱だけ「箱にポン」、放り込んで片づけるルールにしても十分です。
👧 児童期(5~9歳):「自分のもの」という意識が芽生える時期
学校生活が始まり、“自分の持ち物”という感覚が生まれます。
この時期は、責任感と整理力を少しずつ育てていきましょう。
- 「自分専用の引き出し」「自分棚」「自分コーナー」をつくる
- ラベルに文字+イラストを併用する
- “時間で区切る”片づけ(遊んだら夕食前に戻す、など)
「あなたの棚を整えるのはあなたのしごと」と伝えることで、“自分の空間を整える喜び”を覚えます。
🧑 思春期(10歳~):「自立」と「管理感覚」を育てる時期
親が片づけに口を出すと反発しやすい時期。
この段階では、自分で決める仕組みづくりが鍵になります。
- 自分で収納方法を選ばせる
- 親は「仕組みの相談役」になる(命令ではなく対話で)
- 大切なものは“隠せる収納”を取り入れ、心理的安心感を大切にする
この時期は、見た目の整頓よりも、「自分の生活をコントロールできる感覚」を育てることが目的です。
「片づけやすい家」は、子どもの心を育てる家
発達心理学では、環境は「第3の教師」とも呼ばれます。
空間が整えば、行動が変わり、行動が変われば心が育ちます。
片づけやすい家をつくるためのポイントは次の通りです。
- 子どもの動線上に収納を置く(動きながら戻せる)
- 片づけアクションは2ステップ以内に(“ポン→閉める”など)
- 収納の高さ・重さ・見やすさを合わせる
→軽いものは上、重いものは下、よく使うものは目線の高さに - 使う場所の近くに収納を設ける
→おもちゃは遊ぶ場所の横、学用品はリビング学習スペースのそば
散らかることを“成長のサイン”に変える
片づけは“しつけ”ではなく、“発達の支援”です。
子どもの成長に合わせて、仕組みを変えながら見守ることが、
自立の第一歩につながります。
散らかる=世界を学んでいる証
片づけられる=心が育ってきた証
そう考えると、少し気持ちが楽になりますね。
「うちの子、成長しているな」と感じながら、
一緒に“片づけやすい家”を育てていきましょう。
💬 まとめ
子どもの成長視点から見れば、散らかす行為も、片づけの習慣も、どちらも子どもの発達の一部です。
家の仕組みを工夫することで、「片づけなさい」と言わなくても自然と整う空間になります。
それこそが、子どもの力を引き出す住まいづくりなのです。
COLLINOでは女性一級建築士が、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来を見据えたリフォームや模様替えプランを丁寧に作成いたします。
安心と上質を兼ね備えた住まいづくりを、ぜひご相談ください。