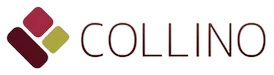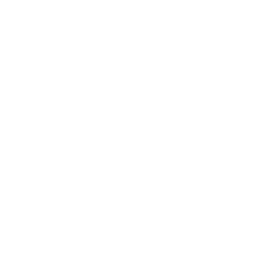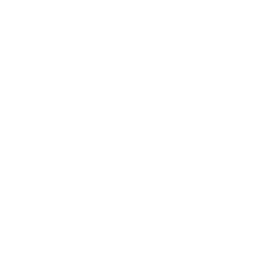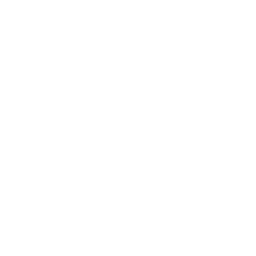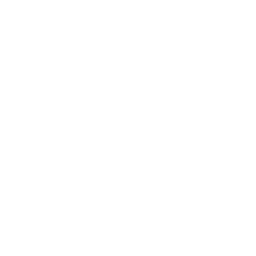難病や寝たきりの子どもと暮らす家――住まいが家族にできるサポートとは
#インテリアコーディネート #ポジティブチェンジ #リノベーション #リフォーム #一級建築士 #医療と暮らしの両立 #医療的ケア児 #家族を支える住まい #寝たきりの子ども #小児がん #模様替え #難病と暮らす家

難病や寝たきりの子どもと暮らす家庭では、医療と生活がひとつの空間で営まれています。吸引器や酸素、モニターなどの医療機器に囲まれながら、家族は24時間体制で子どもをケアします。その負担は大きく、家そのものが家族にとって安心や居心地を与える存在になれていない場合も少なくありません。
本来なら、こうした家庭こそ住まいの設計や部屋づくりに十分な配慮が必要です。ところが現実には、住空間の工夫が後回しにされてしまうことが多いのです。この記事では、その理由と改善のための工夫を、一級建築士の視点から考えてみたいと思います。
なぜ配慮された住まいが実現しにくいのか
必要性は高いのに、難病や寝たきりの子どもがいる家庭で住まいへの配慮が進まない背景には、いくつかの要因があります。
1. 医療優先で「生活設計」が後回しになる
病気がわかった時、まず優先されるのは医療体制の確保です。医師や看護師からは機器設置や介助の方法について指導を受けますが、「暮らしやすさを支える住まいの整え方」についてはほとんど情報が届かないのが実情です。そのため、家は「医療の場」としては整っても、「家族の生活の場」としては後回しにされがちです。
2. 専門家との接点が少ない
医療や介護の専門職とは日常的に関わりますが、建築士やインテリアの専門家に相談する機会はほとんどありません。家具配置や間取りである程度は改善できると知らないまま、不便や違和感を抱えながら暮らしている家庭も多いのです。
3. 経済的・時間的な余裕が不足
24時間体制のケアで心身ともに余裕がなく、住まいの改善にまで手が回らないのが現実です。リフォームには費用がかかると思い込み、模様替えや家具配置の工夫といった低コストの方法に気づけないこともあります。
4. 「家庭らしさ」を守る発想が抜け落ちる
医療機器やベッドがリビングを占有し、家全体が「病院のような雰囲気」になってしまうことがあります。家族も本人も温かさを求めているのに、どう改善すればよいかわからないため、そのままの状態で暮らし続けるケースも少なくありません。
住まいが果たす役割とは
実は、住まいのちょっとした工夫が、ケアの効率だけでなく家族の心の余裕にもつながります。
- 動線の確保:車椅子や医療機器を使う際にスムーズに移動できるよう家具を配置。
- 家具配置の工夫:介助する親が子どものそばに座れるスペースを残す。
- 空気や温湿度の調整:感染症予防と快適性を両立させる。
- 将来を見据えたバリアフリー視点:子どもの成長や介助方法の変化に備えて設計する。
- 季節を感じられる窓や植栽の設置:外に出にくい生活でも、窓から空や庭の緑が見えるだけで、心がほっと和らぎます。ベランダや庭に季節の花を植えたり、室内から見える位置に植栽を配置することで、四季の変化が暮らしに彩りを与えてくれます。自然の移ろいは、子どもにとっても家族にとっても「外の世界とつながっている」安心感となり、毎日の生活に小さな喜びをもたらします。
このように、住まいは医療機器を置く場所という機能にとどまらず、ケアと生活、そして心の豊かさを両立させる舞台となり得るのです。
「家庭らしさ」を取り戻す工夫
医療機器があるからといって、家全体が無機質になってしまう必要はありません。
- 色や素材:壁やカーテンに温かみのある色を取り入れる。
- 照明:柔らかい光で、機器の冷たい印象を和らげる。
- インテリア:家族写真や子どもの好きなキャラクター、かわいい壁紙を取り入れることで「病室」ではなく「家」と感じられる空間に。
- 親やきょうだいの居場所:ケアを担う親がほっとできる椅子や、きょうだいが家族のそばで安心して過ごせる学習コーナーも欠かせません。
住まいに“家庭らしさ”を残すことが、心の支えになり、子どもと家族にとっての生活の質を高めます。
実例紹介:住まいの工夫で変わった家庭
事例A:和室をケアベッドと収納動線に改修
物置同然だった和室を片づけ、介助ベッドと医療機器を整理。必要な機器を「手の届く場所」にまとめたことでケアが効率化しました。余白が生まれたことで親が安心して腰かけられるスペースもでき、絵本を一緒に読んだり、子どもと触れ合う時間が増えました。
事例B:リビングの中心に子どものスペースを配置し、家族の団らんが戻った
以前はリビングを「家族の場」と「医療機器の場」に分けていたため、子どもが孤立しがちでした。そこで発想を変え、子どものケアスペースをリビングの中心に配置。医療機器は背の低い棚に組み込み、配線を隠してインテリアに溶け込ませました。さらに壁の一部にかわいい動物柄の壁紙を取り入れ、柔らかなパステルカラーのカーテンでコーディネート。
兄弟も自然とリビングに集まり、一緒にテレビを見たり遊んだりする“家族の中心”が再生しました。医療の場でありながら、「家庭のリビング」としての温かさを取り戻しました。
事例C:兄弟の居場所を工夫し、家族全員が安心できる空間に
兄弟姉妹が「静かにしていなければ」と気を遣わないよう、リビング近くに小さな学習コーナーを設置。親の目が届く安心感と、自分だけの居場所を持てる独立感を両立させました。これにより、「病気の子のケアを優先するあまり他の家族が我慢する」という状況が和らぎ、家族全体が過ごしやすい空間へと変わりました。
専門家が関わることでできること
家族だけで工夫するのは限界があります。建築士や空間の専門家がすこしでも入ることで、次のような提案が可能です。
- 家具配置や収納を見直し、ケアと生活を両立させる。
- 医療機器を「隠す」だけでなく「自然に溶け込ませる」デザインを考える。
- リフォームではなく模様替えや配置替えで改善する低コストな方法を提示。
専門家の関与によって、住まいは「治療の場」であると同時に「家族が暮らす場」としての役割を果たせるようになります。
まとめ
難病や寝たきりの子どもと暮らす家庭では、医療と生活の両立が大きな課題です。情報不足や負担の大きさから住まいへの配慮が後回しになりがちですが、家具配置やインテリアの工夫だけでも、子どもと家族の生活は大きく変わります。
住まいは「ケアの舞台」であると同時に「家族が共に生きる場所」です。温かさや家庭らしさを取り戻すことが、子どもと家族の未来を支える大切な一歩になります。
社会的取り組みについて
当事務所では、社会的な取り組みの一環として、難病や寝たきりのお子様と暮らすご家庭向けの住まい相談を無料で承っております。
対象は、小児がん、筋ジストロフィー、重度脳性まひなど、長期の療養や医療的ケアが必要なお子様をはじめとするご家庭です。
本相談はアドバイスや工夫のご提案を目的としたものであり、具体的なプラン作成や設計図面の提供は含まれませんが、少しでも暮らしを快適にするヒントをお届けできればと考えております。