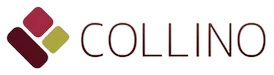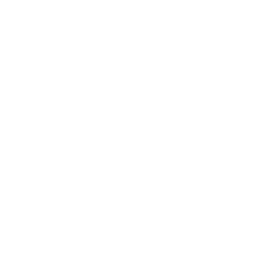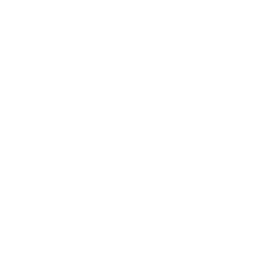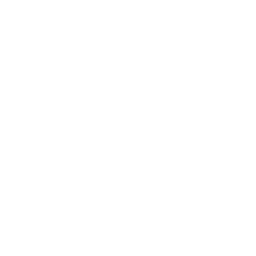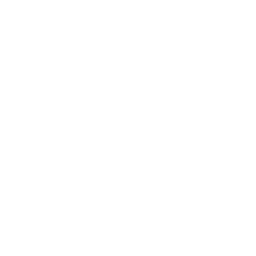「親と同居したら関係が悪化した…」それ、間取りのせいかもしれません――二世帯住宅・親との同居に多い“水まわりストレス”の影響
#インテリアコーディネート #ポジティブチェンジ #リノベーション #一級建築士 #二世帯住宅の失敗 #同居トラブル #模様替え 東京 #水まわりの分離 #親との同居

「玄関の音で毎晩起こされるのが、こんなにつらいとは思わなかった」
「親の介護のために、思い切って実家を建て直して同居を始めました。でも、たった3カ月で、こんなにストレスになるなんて……」
そう話すのは、都内在住の50代女性。ご主人と中学生の娘の3人家族で、昨年末からご自身の高齢の母親と同居を始めました。きっかけは母親の軽い転倒。「何かあってからでは遅い」と、実家を建て替えて同居を決断。しかし、理想とはほど遠い現実が待っていました。
「夜、夫の帰宅が遅いと、玄関の鍵を開ける音で母が目を覚ましてしまうんです。娘が友達を家に呼ぶのも遠慮がちになって…。それでも“玄関は一緒で当然”と思っていたんですが、今は“別にしておけばよかった”と心底思っています」
「顔を合わせるだけ」でストレス!“水まわり共有”の落とし穴
実際に同居が始まると、当初の「気遣い」が「我慢」へと変わっていく家庭は少なくありません。
このご家庭の間取りは、いわゆる“部分共有型”。リビングと寝室は世帯ごとに分かれていましたが、玄関・キッチン・浴室・洗面所・トイレはすべて共用。特に水まわりは、生活時間のズレがそのまま「衝突のタネ」になっていました。
- 親が夕食後すぐにお風呂に入るため、子世帯が使う時間が限られる
- 朝の支度が重なり、トイレ・洗面所が取り合いになる
- キッチンで使う食材や調理法が違い、冷蔵庫もごちゃつく
- 洗濯機が1台しかなく、タイミングを見計らって毎日気を使う
特に玄関に関しては、「一日に何度も顔を合わせる」ことがプレッシャーになり、娘さんが外出や来客を控えるようになったといいます。
同居が“壊す”家族関係──その原因は「性格の不一致」ではない
親と子が仲良く暮らせない理由を、「性格」や「世代間の価値観の違い」とする人は少なくありません。
しかし、一級建築士として多数の二世帯住宅を見てきた私の実感は明確です。最大の原因は、“空間設計の甘さ”です。
たとえば…
- 生活スペースが1階と2階で分かれていても、トイレや浴室が1カ所だけで不便
- 片づけ方や料理の仕方が違い、キッチンが常に小さな不満の火種に
- 生活音やにおい、水の音が伝わることで無言のストレスが蓄積
こうした問題は、建築時に「将来的な生活動線」と「プライバシー」を設計に織り込んでいなかったことによって引き起こされます。
「完全分離型」の二世帯住宅が選ばれる理由
最近では、「最初から完全分離にしておけばよかった」という後悔の声が後を絶ちません。
完全分離型とは、単にリビングや寝室を分けるのではなく、以下の設備を“2つずつ”持つことが原則です。
| 設備・スペース | 推奨対策 |
|---|---|
| 玄関 | それぞれ別の出入口を設ける |
| キッチン | 最低限、ミニキッチンを追加して調理・冷蔵庫は別に |
| 浴室+洗面所 | シャワールームと浴室、洗面台2つが理想的 |
| トイレ | 世帯ごとに1つずつ(2階設置も有効) |
| 洗濯・物干しスペース | 洗濯機・物干し場を別に設け、生活リズムの衝突を回避 |
「そこまで分ける必要あるの?」という声もありますが、暮らし始めてから後悔するのが水まわりの共有です。特に女性は“家事を担う場面”が多いため、ストレスの蓄積が深刻になりがちです。
「仲良くするために分ける」──家族関係を壊さない間取りとは
二世帯住宅というと、ひとつ屋根の下で支え合うイメージがあります。
しかし、実際の生活では「物理的な距離感」が「心理的な距離感」を大きく左右します。
玄関が共用で顔を合わせすぎる
→「行動を見張られている」ように感じる
お風呂やキッチンを譲り合う
→「気疲れして自由に過ごせない」
こうした積み重ねが、親子・嫁姑・孫との関係すべてに波紋を広げます。
だからこそ、「仲良くするために、適度に離れて暮らす」という考え方が重要なのです。
完全分離型の二世帯住宅は、「家族を遠ざける家」ではありません。むしろ、“家族関係を長続きさせる距離感”を保つ設計だと言えるでしょう。
まとめ──“設備は1つで十分”という考えが、家族を疲れさせている
同居を始めるとき、「設備は1つあればなんとかなる」という考えがつきまといます。
でもその“なんとか”の裏側で、家族の誰かが毎日ストレスを抱えています。
玄関・キッチン・お風呂・洗面・洗濯は、最初から2つずつ持つつもりで設計する。
初期のイニシャルコストは膨らみますが、それが、後悔のない同居生活、そして家族関係の崩壊を防ぐための最善策です。
住まいは、人を幸せにも、不幸にもします。
親子同居や二世帯住宅を成功させるかどうかは、「心の問題」「意志の力」ではなく、空間設計のスタート時点で決まっているのです。
COLLINOでは女性一級建築士が、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来を見据えたリフォームや模様替えプランを丁寧に作成いたします。
安心と上質を兼ね備えた住まいづくりを、ぜひご相談ください。