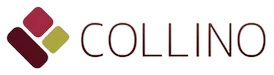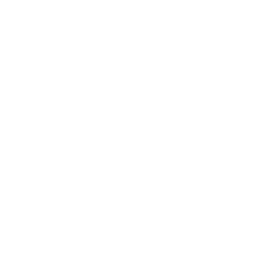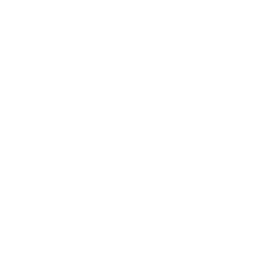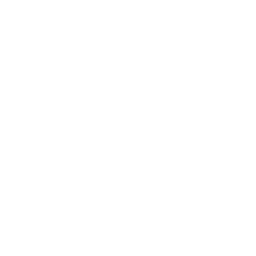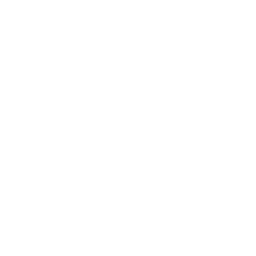「子ども部屋は“永住地”ではなく“通過点”」~子ども部屋おじさん・おばさんにならないために、考えるべき“家の間取り”
#20代の住宅購入 #可変間取り #子ども部屋 #子ども部屋おじさん #子ども部屋おばさん #家づくりの失敗例 #家族関係と住まい #自立できない子ども #間取り設計

近年、「子ども部屋おじさん・おばさん」という言葉を耳にすることが増えました。
成人しても実家の子ども部屋で暮らし続ける中高年を指す言葉です。
非正規雇用の増加や家賃高騰といった社会的背景に加え、
“親の家が快適すぎる”という住環境の問題も、静かにその増加を後押ししています。
こうした現象は、“家のつくり方”にも一因があるかもしれません。特にこれから家を建てたり購入したりする20代の方には、「立派な子ども部屋をつくることが、将来のリスクになるかもしれない」という視点をぜひ持っていただきたいと思います。
■「良い子ども部屋」が、子の“自立”を遠ざける
親としては、子どもに“自分だけの空間”を与えてあげたいと思うのは自然なことです。
静かに勉強できて、趣味も楽しめる。そんな「理想の子ども部屋」を整えることは、
一見、愛情と教育の両立のように見えます。
けれども、その“理想の部屋”こそが、結果的に「出づらい家」を生み出してしまうことがあります。
快適な個室は、勉強にも休息にも最適です。
しかし成長して社会人になった後も、
「駅近で便利」「家賃ゼロ」「ごはんが出てくる」環境が続けば、
外に出て一人暮らしを始める理由が見つかりにくくなるのは当然です。
それは経済合理的であると同時に、心理的依存を強める構造でもあります。
■“出られない家”の構造
「自分の部屋を持たせてあげたい」――。
その思いから、勉強机・収納・ベッド、さらにはテレビアンテナまで完備した“理想の子ども部屋”をつくります。そしてその瞬間から、その部屋は「子ども部屋」として固定化されます。
安全で、快適で、何でも揃っている――。
そんな部屋から子どもが出ていかなくなるのは、ある意味では当然です。
子どもにとってそれは“安心基地”であり、親にとっても子どものためを思って“手をかけた成果”でもあります。
しかし家は本来、家族の成長に合わせて変化していくものです。
子どもが成長し、親が歳を重ね、暮らし方が変わる――それに合わせて、部屋の使い方も変えていく必要があります。つまり、「子ども部屋」は永遠の箱ではなく、ライフステージに応じて姿を変える“可変空間”であるべきなのです。
たとえば、子どもが巣立った後には「在宅勤務部屋」「親の寝室」「趣味室」など、必要に応じて役割を変えていく。それが本来の“家の成長”であり、住まいが人を育て、また人が住まいを育てるという健全な循環です。
■“出やすい家”をつくる発想
では、どうすれば「出られない家」にならずに済むのでしょうか。
ヒントは、「出やすい家=変えやすい家」という発想にあります。
・子ども部屋を“完全個室”にせず、可動式の間仕切りや収納家具でゾーニングする
・ロフトなどを避け、将来はワークスペースや寝室に転用できるようにする
・子どもが巣立ったあとは、親の個室や趣味室・賃貸などに“用途転換”できる設計にする
こうした設計は、将来の家族構成の変化にも柔軟に対応できます。
実際に、私が設計した住宅でも、
「子どもの巣立ち後は親の寝室に」「在宅ワークが増えたから書斎に」「空いた部屋を賃貸に」など、
“再利用できる子ども部屋”の需要は増えています。
■“固定しない部屋”が、家族の関係を動かす
建築的な観点から見ると、“固定された空間”は家族関係や人の行動を固定します。
つまり、間取りが変わらなければ、家族の関係も変わらないのです。
リビングに近い位置にあった子ども部屋が、いつまでもそのままだと、
親も「まだ子どもがそこにいる」ような感覚を持ち続けます。
反対に、家具を入れ替えたり、机を撤去したりするだけで、
空間は“親のスペース”として再定義され、心理的にも区切りがつきます。
子どもの成長に合わせて空間を更新していくこと。
それは「出ていきなさい」と突き放すのではなく、“自立を応援する環境づくり”でもあります。
■老後を見据えた“コンパクトな住まい”という選択
また子どもが巣立ったあとの暮らしを考えると、
実は「広い家」ほど維持コストが重くのしかかってきます。
広ければ光熱費も高くなり、冷暖房効率も悪化します。
さらに築年数を重ねるごとに、屋根や外壁、水まわりなどの修繕・リフォーム費が必要になります。
若い頃には気にならなかった階段の上り下りも、年齢を重ねるにつれて大きな負担になります。
たとえば、平屋やコンパクトな家は、将来にわたって管理がしやすく、生活動線も短く済みます。
「子ども部屋をつくるために家を大きくする」のではなく、まず「夫婦二人の生活」をベースに考える。子どもが生まれたら、いくつかの“夫婦の部屋”を一時的に子ども部屋として使い、巣立ったら再び夫婦の住まいに戻す――。
そんな設計のほうが、家は長く健やかに呼吸し続けます。
家は一度完成したら終わりではなく、暮らしに合わせて“更新していく”もの。
いずれにしても、家族の変化に合わせて柔軟に使い方を変えること――それが、長く快適に暮らせる家づくりの基本です。
■まとめ:「子ども部屋は、人生の“途中駅”である」
子ども部屋を“与えること”が目的ではありません。
“安全な空間で育ち、食べていけるようになったら、自然にそこから出ていけるように設計すること”こそが、本当の親心です。
立派な子ども部屋をつくるよりも、
家族が変化することを前提に、「変えられる家」を意識して設計すること。
それが、子どもの自立を助け、親にとっても“次の暮らし”へ移行しやすい家づくりにつながります。
■教育建築士としてのメッセージ
家は「完成させるもの」ではなく、「育てていくもの」です。
その時々の家族に合わせて、少しずつ形を変えながら成熟していく。
住まいが変わるたびに、家族も一緒に成長していける。
そんな“変われる家”を、20代のうちから意識してほしいと思います。
COLLINOでは女性一級建築士が、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来を見据えたリフォームや模様替えプランを丁寧に作成いたします。
安心と上質を兼ね備えた住まいづくりを、ぜひご相談ください。