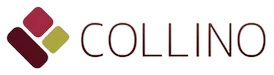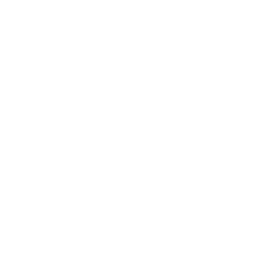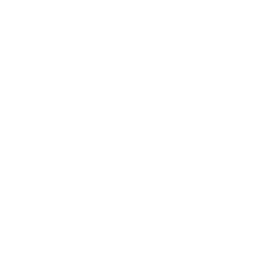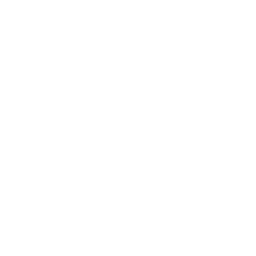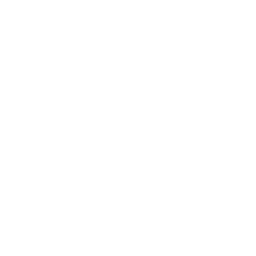使わなくなった子ども部屋、どう活用する?“もったいない空間”を生かす再活用ガイド
#リフォーム #一級建築士 #二人暮らし #子ども部屋 #家族関係と住まい #暮らしの見直し #書斎 #模様替え #空き部屋活用 #賃貸活用 #趣味部屋 #間取り変更

子どもが成長して独立し、ぽっかり空いてしまった子ども部屋。
「そのうち何かに使いたい」と思いながらも、気づけば物置になっていませんか?
国土交通省の調査では、子どもが巣立った後も「使っていない部屋がある」と答えた家庭は8割以上。つまり多くの家庭で、“もったいない空間”が眠ったままになっているのです。
しかしこの空間、少しの工夫で“第二のリビング”にも、“夫婦の趣味部屋”にも、“小さな賃貸収入の場”にも生まれ変わります。
今回は、空き子ども部屋を活用するための考え方と、実際の模様替えの進め方を、現場で多くのリフォーム・模様替えを手がける建築士の視点からご紹介します。
1. まず考えたい「これからの暮らし」と「部屋の条件」
子ども部屋を活かす第一歩は、「この部屋を誰が、いつ、どう使うか」を具体的にイメージすることです。
夫婦だけの時間が増える50代以降は、暮らし方が大きく変わるタイミング。寝室の使い方を変えたり、趣味の時間を増やしたり、在宅ワークの場を整えたりと、目的によって必要な空間設計も異なります。
その前に確認したいのが、部屋の条件と制約です。
・広さ(どのくらいの家具が置けるか)
・窓や扉の位置(風通し・採光)
・コンセントの数や場所
・冷暖房・換気設備の有無
・防音・断熱などの性能
リフォームを伴う場合は、間仕切りの撤去や配線工事が必要なこともあります。
まずは「できる範囲」を知ることが、ムダのない計画の第一歩です。
2. 活用スタイル別のアイデア集
① 趣味・書斎スペースとして
子育てが一段落したあと、「自分の時間を過ごせる場所がほしい」と考える人は多いもの。
空いた部屋を趣味や仕事に集中できる空間として整えるのは人気の活用法です。
本棚や作業机を中心に、照明とコンセント位置を見直せば、静かで心地よい“マイスペース”が完成します。
楽器演奏や動画編集など音を使う趣味なら、防音壁や防音カーテン、吸音パネルを取り入れるのも効果的です。また壁面収納を上手に使えば、限られたスペースでもスッキリとまとめられます。
② 夫婦で寝室を分けて個室化
同じ寝室で過ごしてきたご夫婦でも、「生活リズムの違い」や「睡眠環境の好み」で別室を選ぶ人が増えています。
空いた子ども部屋をもう一方の寝室にすることで、お互いの生活音や照明を気にせず休めるようになります。
特に更年期以降は、睡眠の質が健康に直結します。
寝室を分けることで、「夫婦の距離ができる」のではなく、「お互いを大切にできる時間が増える」──そんな前向きな空間づくりになります。
③ ゲストルームとして再活用
遠方で暮らすお子さんが帰省したときや、友人・親族が泊まりに来たときに使えるよう、ゲストルームとして残しておくのもおすすめです。
常時使わない場合は、折りたたみベッドやソファベッドを使うことで、普段は書斎としても使えます。
寝具やタオル、ちょっとしたアメニティをひとまとめに収納しておけば、急な来客にもスマートに対応できます。
④ 賃貸やシェアスペースとして貸す
玄関に近い部屋や、階段を介して直接外から出入りできる部屋がある場合は、
家の一部屋を「時間貸し」として活用することも可能です。
たとえば、在宅ワークや習い事のために“静かな個室を借りたい”というニーズは増えており、
「1日単位で貸す」「月単位で貸す」など、柔軟な形で運用する家庭も増えています。
家具付きで貸し出す場合は、汚れや破損のリスクを考慮し、床や壁は原状回復しやすい素材(クッションフロア・塗装仕上げなど)を選ぶと安心です。
また、出入り動線の独立性やプライバシーの確保を意識することで、お互いにストレスのない共用が実現できます。
3. 使わない子ども部屋を活かす3ステップ
ここからは、実際に模様替えを始めるときの具体的な進め方です。
多くの方が「どこから手をつけたらいいのかわからない」と感じますが、次の3ステップを踏めばスムーズに進みます。
STEP1:部屋の寸法を測り、家具配置をイメージする
まずは部屋を“図面化”することから。
メジャーやレーザー測定器で、壁の長さ・窓やドアの位置・天井高・コンセント位置を記録します。
既存の家具も採寸して、手書きでもよいので配置図を描いてみましょう。
「どこに何を置くか」を具体的に想像するだけで、必要な家具・不要な家具が自然と見えてきます。
動線(出入りしやすさ)を意識しながら配置を考えるのがコツです。
STEP2:不要な家具や本を処分する
次に、思い切ってモノを減らすステップです。
長年置きっぱなしになっていた教科書やぬいぐるみ、学習机などを整理します。
- 自治体の粗大ごみ回収を利用して少しずつ出す
- 不用品回収業者にまとめて依頼して一気に片付ける
- リサイクルショップやフリマアプリで再利用
処分が進むと、部屋の印象が一気に軽くなり、模様替えへのモチベーションも上がります。
「とりあえず保管」したいものは“保留ボックス”をつくって、3カ月後にもう一度見直すとよいでしょう。
STEP3:家具を配置して完成させる
空間が整ったら、いよいよ家具の配置です。
レイアウト図をもとに、必要な家具だけを厳選。多機能家具やキャスター付き収納などを選ぶと、後から模様替えもしやすくなります。
最後に、照明・カーテン・ラグなどのインテリア要素で空間を仕上げましょう。
照度を調整できるスタンドライトや、断熱・防音機能のあるカーテンを選ぶと、快適性がぐっと上がります。
4. 失敗しないためのポイント
- 壁に家具をぴったりつけすぎない:空気の通り道を確保して湿気を防ぐ
- 可変性を残す:将来、また用途を変えられるよう、造作家具は最小限に
- 照明・コンセントを最初に設計:後から延長コードで対応すると見た目も危険性も増す
- 防音や断熱を意識:寝室・趣味部屋にするなら、カーテンやラグで調整
- 片付けやすさを優先:収納の“動線摩擦”を減らすと、きれいが続く
5. 子どもが独立した後の部屋の使い道
使わなくなった子ども部屋は、手を入れれば“暮らしを再設計するきっかけ”になります。
夫婦の時間を大切にしたり、自分の趣味を楽しんだり、あるいは家計にプラスをもたらす空間に変えることもできるのです。
使わなくなった子ども部屋の再活用は
- 部屋を測る
- モノを減らす
- 配置を描く
──この3ステップから始めてみてください。
思い出の詰まった子ども部屋が、これからの人生を豊かにする「新しい居場所」に生まれ変わります。
COLLINOでは女性一級建築士が、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来を見据えたリフォームや模様替えプランを丁寧に作成いたします。
安心と上質を兼ね備えた住まいづくりを、ぜひご相談ください。